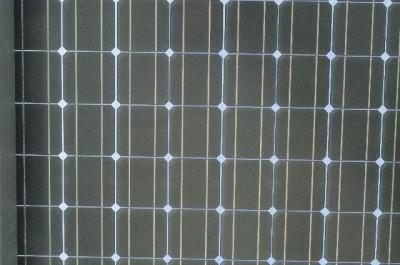2015年10月22日 20:15
ペロブスカイト構造とは
ペロブスカイト構造とは、結晶構造の一つです。ペロブスカイト(灰チタン石CaTiO3)と同じ結晶構造をペロブスカイト構造と呼んでいます。たとえばBaTiO3(チタン酸バリウム)のように、(A)(B)(X3) という3元系から成る遷移金属酸化物などが、この結晶構造をとります。発電の原理
ペロブスカイト太陽電池は、結晶がペロブスカイト構造の有機-無機化合物(CH3NH3PbX3(X =ハロゲン)など)から成っています。この構造のイオンはBサイトに鉛(Pb2+)、Xサイトにヨウ素(I-)、 Aサイトにメチルアンモニウム(CH3NH3+)が入り、それが立方晶配列を形成しています。ペロブスカイト層で吸収された光は、原子から電子を運び去り、正の電荷を帯びた電子空孔(正孔とも呼んでいるもの)を作ります。それから、電子を一方の電極に導き、正孔をもう一方の電極に導けば、電気が発生します。
ペロブスカイト太陽電池のメリット
ペロブスカイト太陽電池は、既存の太陽電池に積層することでエネルギー変換効率が向上できます。現在、日本の実験では15%の変換効率が確認されてます。また光の吸収能力にすぐれ、500nm(ナノメートル)の厚みでほぼ100%の光が吸収できます。この太陽電池は、シリコン系に必要な高温加熱や高真空プロセスが要りません。基板の上で多孔質の酸化チタンに溶液を塗布し乾かすだけで作製できるため折り曲げ加工が可能で、非常に安価に製作できます。さらに1ボルト程度の高い開放電圧が得られることも魅力です。
ペロブスカイト太陽電池のデメリット
ペロブスカイト太陽電池には上記のような有益な面が多々ありますが、開発間もないため実用化には何点か課題もあります。何回か実験を重ねると、劣化が非常に速く耐久性に大きな問題が見つかりました。また電圧のかけ方によって変換効率がバラツクといった問題もでています。実用化に向けての期待
ペロブスカイト太陽電池は2009年に日本の宮坂力教授らの研究チームがペロブスカイト結晶の薄膜を発電部に使用し、太陽電池として動作することを突き止めました。ほかの固体接合太陽電池と異なり、化学工程で作ることを特徴とする「化学で作る太陽電池」の典型です。この太陽電池最大の魅力は、塗布するだけで作成できることです。この技術によって電池はカラフルに仕上がり、バッテリーカーのボディーに塗り太陽光で充電し走行することが可能です。また、PCなどに塗って室内光でIT機器を使用するといったことも出来ます。
発見当初、変換効率は4%程度でしたが、ほんの数年で15%まで上がっています。未確認ですが韓国の研究チームは、20%の変換効率を達成したという情報もあります。今後、さらに効率は上がると想定されており、実用化できれば太陽光発電の目玉になることは間違いありません。
-->
記事検索
アクセスランキング トップ10
特集
お問い合わせ